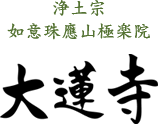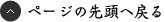應典院でがん患者サロンが始まりました。がん患者さん、またそのご家族が集まって、いろんな話し合いが生まれています。主催の緩和ケア医の森一郎先生のご縁で、今後も偶数月に開催されます。
日本人の二人に一人ががんになると言われます。治療技術は進歩したとはいえ、やはり誰でも思い煩いは募るもの。病院では段取り優先で進んでいきますから、質問したり相談することも憚ります。「よくわからないうちに治療が進んでいく」という方も多いのではないでしょうか。ましてや緩和ケアなど「怖くて聞くこともできない」という本音も耳にします。
これは医療と患者のみならず、市民社会が分断しているから、と森先生は考えています。とりわけ大病院では科学的合理主義こそ絶対であって、一人一人の不安や揺らぎ、戸惑いに向き合うことはありません。それを批判することはしませんが、本当の医療/ケアはそれでは完成はあり得ません。
教育が学校というシステムの中で完成しないように、病院の中では本当のケアは開かれない、それには地域との交流や対話の機会が大切なのだ、と森先生のお考えなのでしょう。それはコミュニティケア寺院を目指してきた、大蓮寺や應典院の考え方と一致するものでした。
専門家である医師と患者には見えない上下関係がありました。がんともなれば、治療だけでなく、生活やお金、仕事などいろんな問題が出てきます。後悔せず納得できる医療を受けるには多くの情報が必要になります。不安や疑問はあるはずですが、それは病院の中で解決できることではありません。
こうした同じ境遇や立場にある人(当事者)が出会い、交流して共に支え合う仲間を、セルフヘルプ(自助)グループと言います。同じがんの経験者から聞く経験談は、先の見えない不安に悩む人に大きな安堵をもたらすでしょう。同じ境遇の人に心情を聞いてもらうだけで、自分だけじゃないと安心することも多いでしょう。これは病院の治療にはない、心のケアなのです。
私は、他にも不登校やひきこもりの会や自死遺族の会などセルフヘルプに関わったことがありますが、いずれも共通するのは「弱い立場」にある人ばかりであるということす。みな外で声を上げることが怖かったり、孤独や不安を抱えてきた人たちです。
しかし、「弱さ」は非力なのではありません。経験者同士が語り合うだけで大きな共感が生まれますし、互いを思いやる心が芽生えます。それは「弱さ」を認めあってこそのつながりであり、相互理解なのかと思います。このサロンでも、「救われた気持ちがする」という声が多く聞かれると言います。
大切なケアの場を専門施設だけに依存するのではなく、自分たちの手で地域に広げていきたいと思います。お寺で開催するがんサロン。次回は4月13日(日)10時から12時まで開催です。